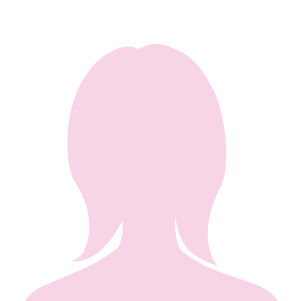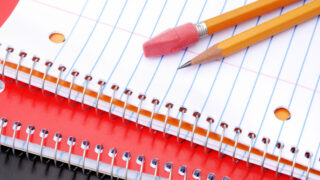剣道を始めたての頃は、剣道の基本を覚えるので大変だったと思います。
今度は、審査に向けて「日本剣道形」という新しいのが増えて、「剣道って意外と奥深いのかも?」なんて思ってる人もいるかもしれません。
その日本剣道形も二部構成になっていて、1~7本目の太刀を使った形と小太刀を使った1~3本目の形があります。
今回は日本剣道形とはそもそも何なのか、それと昇段審査の記事でまだ触れていない小太刀の形について書きたいと思います。
Contents
そもそも日本剣道形って何?歴史について調査しました!
 昇段審査の記事で、日本剣道形1本目~7本目について説明しました。
昇段審査の記事で、日本剣道形1本目~7本目について説明しました。
ふと、こんな疑問が湧いた人がいるかもしれません。
そこで、昇段審査の回では説明していなかった、日本剣道形の成り立ちについてお伝えします。
全日本剣道連盟のサイトには、このように記されています。
大正元年(1912)には剣道と言う言葉が使われた「大日本帝国剣道形(のち「日本剣道形」となる)」が制定された。
流派を統合することにより日本刀による技と心を後世に継承すると共に、竹刀打ち剣道の普及による手の内の乱れや、刃筋を無視した打突を正した。
竹刀はあくまでも日本刀の替りであるという考え方が生まれ、大正8年、西久保弘道は「武」本来の目的に適合した武道および剣道に名称を統一した。
簡単に言ってしまえば、江戸時代に入るまで様々な流派が存在していたのを、後世に伝えるために、当時のお偉いさんたちが集約したもの、それが日本剣道形です。
つまり、日本剣道形には、いろいろな流派の特徴が盛り込まれているわけです。
例えば、坂本龍馬が使い手で有名だった北辰一刀流、薩摩藩で広く使われていた示現流、今でも多くの人が稽古している神道無念流、などなど。
含まれている流派のなかには、あなたが知っているものや、居合道をやっている人はあなたが学んでいるものもあるかもしれません。
いろいろな流派があったとはいえ、武士の時代が終わり、平和が訪れた世界では、刀を使って人と対峙するわけにはいきません。
刀は使えない、だけど「刀である」という意識は持っていてほしい!
そんなこんなで、木刀で行う形稽古が誕生しました。
形稽古が誕生したことで、竹刀の打ち方にも変化が起こり、今の剣道につながっていったのです。
日本剣道形のルーツは日本刀の流派にあり!
それぞれの流派をまとめたものが日本剣道形として制定された!
日本剣道形の小太刀の形1本目~3本目について解説します!
 日本剣道形には小太刀の形というものが存在します。
日本剣道形には小太刀の形というものが存在します。
武士が持っていた刀身の短いものでの立ち回り方を体系化したものです。
小太刀とは……
小太刀とは太刀の一種です。
太刀は刃渡り約60cm以上の大きめの刀のことですが、小太刀とは刃渡り30cm以上60cm未満の刀身の短い刀のことを指す言葉です。
現代では脇差と同じものとして分類され区別は曖昧になっていますが、太刀や大太刀が流行していた時代(戦国時代頃まで)には、60cm以下の短い太刀のことをこのように呼んでいたのです。
実際に昇段審査で必要になるのは剣道四段からになります。
私自身も次に受ける昇段審査は四段からなので、覚える必要があります。
ここでは、小太刀の形1本目~3本目について説明します。
小太刀の取り扱い方について
- 小太刀を置くときは、太刀の内側にする
- 太刀の形から小太刀の形に移るとき、打太刀は、立会の間合でそんきょして待つ
- 太刀の形から小太刀の形に移るとき、仕太刀は二、三歩後に下がり、小太刀の位置に至る
- 小太刀の位置に至ったら、打太刀側に向き、上座と反対側の片ひざをついて、小太刀に持ちかえる
- 構える場合は抜き合わせると同時に、左手を腰にとる
- 構えを解くときは、剣先を下げると同時に左手を下ろす
- 左手を腰にとる要領は、刀の場合は栗形の部分を親指を前にして軽く押さえる
- 左手を腰にとる要領は、木刀の場合は親指を後ろに、四指を前にして腰にとる
小太刀の形1本目
❶打太刀は諸手左上段、仕太刀は中段半身の構えで、打太刀は左足から、仕太刀は右足から、互いに進み間合いに接する
❷仕太刀が入身になろうとするので、打太刀は右足を踏み出すと同時に、諸手左上段から仕太刀の正面に打ち下ろす
❸仕太刀は右足を斜め前に、左足をその後ろに進めて、体を右に開く
➍仕太刀は右手を頭上に上げ、刃先を後ろにして、左鎬で受け流して打太刀の正面を打つ
❺仕太刀は打太刀の正面を打った後、左足から一歩引いて上段を取って残心を示す
❻その後、いったんその場で相中段になってから、打太刀、仕太刀ともに左足から元の位置に戻る
小太刀の形2本目
❶打太刀は下段、仕太刀は中段半身の構えで、互いに右足から進み間合いに接する
❷打太刀は下段から中段になろうとする瞬間、仕太刀は打太刀の刀を制して入身になろうとする
❸打太刀は右足を後ろに引いて脇構えに開くのを、仕太刀が再び中段で入身になって攻める
➍打太刀は脇構えから変化して諸手左上段に振りかぶり、右足を踏み込むと同時に仕太刀の正面を打つ
❺仕太刀は左足を斜め前に、右足をその後ろに進めて、体を左に開く
❻仕太刀は体を開くと同時に、右手を頭上に上げ、刃先を後ろにして、右鎬で受け流して面を打つ
❼仕太刀は、打太刀の二の腕を押さえて腕の自由を制すると同時に、右拳を右腰にとり、刃先を斜め下に向け、剣先を咽喉部につけて残心を示す
❽打太刀は左足から、仕太刀は右足から、相中段になりながら刀を抜き合わせた位置に戻る
小太刀の形3本目
❶打太刀は中段、仕太刀は下段半身の構えになる
❷打太刀は右足、左足と進み、次の足を踏み出すとき、仕太刀が入身になろうとするのを中段から諸手右上段に振りかぶり、仕太刀の正面に打ち下ろす
❸仕太刀は刀をいったんすり上げて、打太刀の右斜めにすり落とす
➍打太刀は、直ちに左足を踏み出し、仕太刀の右胴を打つ
❺仕太刀は左足を左斜め前に踏み出し、体を右斜めに開く
❻仕太刀は、体を開くと同時に、胴に打ってくる打太刀の刀を、左鎬ですり流し、そのまま左鎬で打太刀の喉元にすり込む
❼仕太刀は、小太刀の刃部の鎬で打太刀の鍔元を押さえて、入身になり、打太刀の二の腕を押さえる
❽打太刀が引くので、仕太刀はそのまま攻めて、二、三歩進み右拳を右腰に取り、刃先を右斜め下に向けて、剣先を咽喉部につけ残心を示す
❾打太刀は右足から、仕太刀は左足から相中段になりながら刀を抜き合わせた位置に戻る
小太刀の形は見慣れないものじゃないでしょうか?
特に、腕を押さえる動きは1本目~7本目にはなかった動きなので、特に注意しながら取り組むようにしましょう!
小太刀の形も繰り返し練習して、昇段審査の本番で間違えないようにしよう!
もちろん審査前には小太刀の準備も忘れずに!
いかがだったでしょうか?
今回は日本剣道形の成り立ちと小太刀の形について説明しました。
小太刀の形はすべて片手で行うので、少し不思議な感じがしたかもしれません。
私自身は最初に見たときそう思いました。
でも、珍しいからこそ印象に残りやすいと思います!
稽古をするときは、小太刀の形も含めて日本剣道形のもとになったいろいろな流派に想いをはせながら、やってみるといいかもしれませんね!